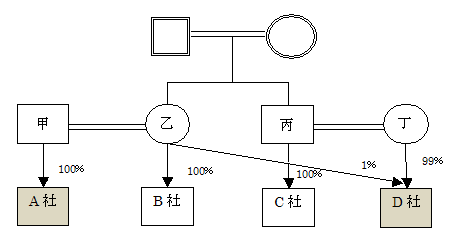日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


※T&Amaster(ロータス21)2010.11.15 No.378に掲載
平成22年度改正により、「同一の者」が個人となっている場合の完全支配関係に従来とは異なる部分が生じていると聞きましたが、もう少し詳しく教えていただけませんか。
要 旨
平成22年度改正の前後で、「同一の者」が個人となっている場合の支配関係と完全支配関係の捉え方に相違が生じているのは事実である。
以下、合併を行うケースを取り上げて、平成22年度改正前の完全支配関係の判定と同改正後の完全支配関係の判定を比較する形で解説を行うこととする。
1 平成22年度改正前の完全支配関係の判定
(1)平成22年度改正前の被合併法人と合併法人との間の関係の捉え方(1)平成22年度改正前の被合併法人と合併法人との間の関係の捉え方
平成22年度改正前は、法人税法2条(定義)の12号の8イにおいて、100%グループ内の適格合併を定めており、その100%グループ内の適格合併となる合併における被合併法人と合併法人との間の関係については政令に委任している。
旧法人税法施行令4条の2(適格組織再編成における株式の保有関係等)の2項においては、次のとおり、この関係を2つの号に分けて規定している。
一 合併に係る被合併法人と合併法人(省略)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されること(省略)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
旧法人税法施行令4条の2第2項各号に掲げられている関係は、上記のとおり、いずれも被合併法人と合併法人との間の関係ということになっているわけであるが、これは、法人税関係法令に「適格合併」としてその取扱いを定めることとなるのは被合併法人と合併法人のみであり、これらの法人がどのような関係にあるのかということを定めれば、それで必要かつ十分であることによるものである。
そして、旧法人税法施行令4条の2第2項は、上記のように1号の関係と2号の関係に分けて被合併法人と合併法人との間の関係を定めているわけであるが、これは、被合併法人と合併法人がいずれも100%グループ内の法人となっているケースのすべてを捉えるためには被合併法人と合併法人との間の関係を1号と2号の双方の関係とする必要があるためである。
この1号の関係と2号の関係に関しては、1号の関係が被合併法人又は合併法人の一方の法人から他方の法人を見ており、2号の関係が株主(「同一の者」)から被合併法人と合併法人を見ているという違いがある点に注意しておく必要がある。
また、旧法人税法施行令4条の2第2項1号の末尾の「次号に掲げる関係に該当するものを除く。」という重複排除の括弧書きに関しては、被合併法人と合併法人との間の関係は同項1号の関係又は2号の関係のいずれかで良いため、法技術的な観点からすれば設けなくても支障がないものであるが、「グループ」については一番外枠の資本関係を「グループ」の外縁と捉えてその中に存在する法人は一体であるとするのが理論的にも正しく、また、実態にも即したものであると考えられるため、敢えてこの重複排除規定を置いているものである。
質問は、個人が株主となっている場合の適格判定ということであるため、平成22年度改正前の規定に基づいて判定することとすれば、上記の旧法人税法施行令4条の2第2項2号の関係に該当するのか否かということが問題となり、同号の「同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)」をどのように解釈するのかということが問題となる。
このため、この旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」とその括弧書きについて、説明を続けることとする。
<参考>
平成22年度改正により、旧法人税法施行令4条の2第2項2号の規定が4条の3第2項2号に移っているが、4条の3第2項2号において、「同一の者」と「一の者」(法令4の3②二ロ)の双方の用語が用いられているために、これらがどのように違うのかという疑問を持つ方が多いことから、これについて、一言、付言しておくこととする。
法令の規定においては、「同一の者」という用語が用いられることもあれば、「一の者」という用語が用いられることもあるわけであるが、それらの条項を見て分かるとおり、特に有為な差があるというわけではない。旧法人税法施行令4条の2第2項2号において、「同一の者」という用語を用いたのは、2号の関係は、1号の関係と異なり、被合併法人と合併法人にそれぞれ株主が存在するという状態を前提として定めるべきであると考えたためである。被合併法人と合併法人には、1号の関係がある場合とは異なり、それぞれ株主が居るが、その株主が同じである場合には、それらの法人は100%グループ内の法人であるとする、としたわけである。
平成22年度改正において、法人税法施行令4条の3第2項2号において、「同一の者」と「一の者」とを混用した理由が何かということは明確ではないが、それらの内容がどのようなものかということは重要となるものの、用語がこのいずれとなっているのかということ自体に大きな意味はないと考える。
この「同一の者」とは、それが法人である場合を想定すると明らかであるが、100%グループの頂点にあってそのグループを支配していると考えられる者である。
この「同一の者」が個人である場合には、基本的にはその個人が100%グループ内の全法人を支配する状態となっているということになるが、同族会社の判定の場合にもあるように、個人の場合には、その個人の親族も実態としてはその個人と一体という状態になっていることが通例であると考えられるため、その個人にその親族を含めて一体として100%グループ内の全法人を支配するという状態となっている場合のその100%グループ内の被合併法人と合併法人の関係も合併を適格合併とする関係としよう、としているわけである。
ただし、この「同一の者」が個人である場合には、その解釈にやや幅があるという点に留意する必要がある。
この旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」は、被合併法人又は合併法人の株主に限られていないため、その括弧書き中の「個人」は、被合併法人又は合併法人の株主でなければならないというわけではなく、その被合併法人の株主でもなければ合併法人の株主でもない「個人」がその親族とともに被合併法人と合併法人の全株式を持っていれば、その「個人」と親族が「同一の者」として全株式を持っていることとなり、被合併法人と合併法人との間には同号の関係があるということになる、というように、同号の関係をかなり広く解釈することも、可能である。
他方、組織再編成税制に関しては、株式の所有を通じて支配されている「グループ」の中の法人の合併はそのような関係にない法人の組織再編成とは異なる取扱いをする必要があるという基本的な考え方で制度が創られており、旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」の括弧書きに関しても、「個人」が法人のすべての株式を保有することでその法人のグループを支配し、そのグループの中に被合併法人と合併法人が存在しているという状態が想定されていることは間違いないことからすると、この「同一の者」は、少なくともグループ内の法人となる法人の株主でなければならない、という解釈を採ることができる。
旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」の括弧書き中の「個人」に関しては、平成22年度改正前の実務においても、その対象者をグループ内の法人の株式を保有していない者まで広げて捉えることは行われていなかったものと思われ、上記の後者のような解釈を採り、法人の株式を保有する者の内の1人をこの「個人」として、その親族を含めた者を「同一の者」としてすべての株式を保有している法人をグループ内の法人と捉え、そのグループ内の法人の合併であれば、100%グループ内の適格合併となる、とされていたものと思われるが、このような解釈と取扱いが制度趣旨にも合致するものと考えられる。
(2)平成22年度改正前の規定による完全支配関係の判定
上記(1)のような解釈を踏まえて、以下の3つのケースについて、平成22年度改正前の規定によって完全支配関係の判定を行うとすればどのようになるのか、ということを考えてみよう。
① ケース1
ケース1は、図表1の場合に、A社とD社が合併するというケースである。
【図表1】ケース1
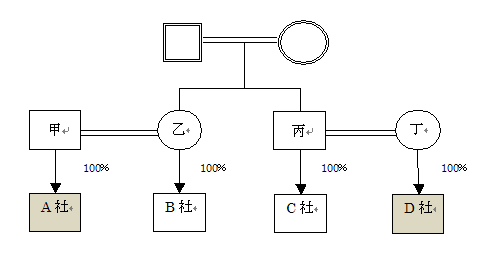
このケース1においては、法人の株主となっているのは甲、乙、丙、丁の全員であるため、これらの者のうちのいずれかを旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」の括弧書き中の「個人」と見たときに、法人の全部の株式がの個人」と親族に保有されているということになると、その「個人」と親族が「同一の者」となり、その「同一の者」にその全部の株式を保有されている法人には同号の関係がある、ということになるわけであるが、改めて言うまでもなく、乙又は丙を「個人」とすると、他の3人はいずれも親族(注)となるため、A社とD社には同号の関係がある、ということになる。
(注)「親族」の定義は民法725条(親族の範囲)によることとなり、「六親等内の血族」、「配偶者」、「姻族」とされているが、甲と乙及び丙並びに丁と乙及び丙とは親族となるものの、甲と丁とは、婚姻によって配偶者の血族との間に成立する「姻族」という関係にもないため、親族の関係にはない、ということになる。
平成22年度改正前の組織再編成税制においては、被合併法人と合併法人との間の相互関係によって適格合併であるのか否かを判定するという2(2)②で述べる考え方は採られていなかったため、旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」の括弧書き中の「個人」を被合併法人又は合併法人の株主に限ると解釈するということはなかったものと考えられる。仮に、そのように解釈するということになると、上記のケースでは、合併は100%グループ内の適格合併とはならない、ということになるが、平成22年度改正前は、このような状態は、乙又は丙から見ると、4つの法人が100%グループを構成する状態と捉えられており、この結論は、明らかに同改正前の組織再編成税制の考え方にそぐわないものとなる。グループを支配している「個人」が乙又は丙であるということであれば、その親族である甲と丁を含めた者が「同一の者」となることとなり、この「同一の者」が4つの法人を支配するということになるが、現に乙又は丙がグループを支配しているという場合を想定すると、甲が全株式を保有するA社と丁が全株式を保有するD社を含めて1つのグループとして乙又は丙が4つの法人を支配するという状態となることが通例であると考えられる。
② ケース2
ケース2は、図表2の場合に、A法人とD法人が合併するというケースである。
【図表2】ケース2
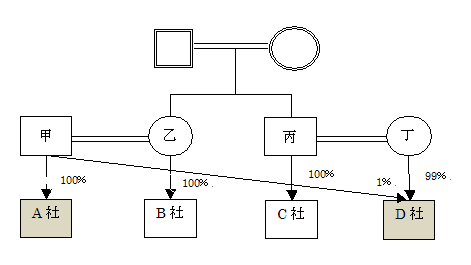
このケース2においても、上記のケース1の場合と同様に、乙又は丙を旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」の括弧書き中の「個人」とすると、他の3人はいずれも親族となるため、A社とD社には同号の関係がある、ということになる。
③ ケース3
ケース3は、図表3の場合に、A法人とD法人が合併するというケースである。
【図表3】ケース3
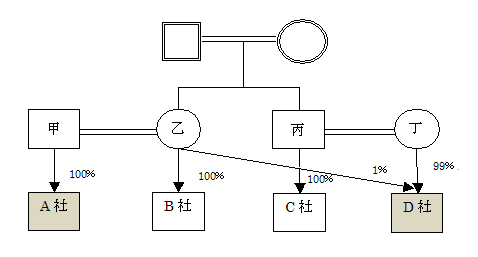
このケース3においても、上記のケース1及びケース2の場合と同様に、乙又は丙を旧法人税法施行令4条の2第2項2号の「同一の者」の括弧書き中の「個人」とすると、他の3人はいずれも親族となるため、A社とD社には同号の関係がある、ということになる。
2 平成22年度改正後の完全支配関係の判定
(1)平成22年度改正後の被合併法人と合併法人との間の関係の捉え方
平成22年度改正後は、法人税法2条12号の7の6において「完全支配関係」を次のように定義している。
十二の七の六 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
この法人税法2条12号の7の6の「政令で定める関係」は、法人税法施行令4条の2第2項前段において、次のように規定されている。
2 法第二条第十二号の七の六に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(省略)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係とする。
(注)この法人税法施行令4条2第2項の規定は、その規定の仕方に疑問が残るものとなっているが(『税理 2010.9 臨時増刊号~グループ法人税制完全マニュアル~』(ぎょうせい)Q9・10参照)、「完全支配関係」とは、要は「発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係」(法法2十二の七の六)であると捉えておけばよいと考えられる。
この「完全支配関係」の定義を用いて、法人税法2条12号の8イ及び法人税法施行令4条の3第2項において、次のとおり、100%グループ内の適格合併と被合併法人と合併法人との間の関係が定められている。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人(省略)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
2 法第二条第十二号の八イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一 合併に係る被合併法人と合併法人(省略)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(省略)がある場合における当該完全支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(省略)があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(省略)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
イ~ニ 省略
<参考>
法人税法2条12号の7の6で「完全支配関係」を「一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係」又は「一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」という2つの枠組みで捉え、法人税法施行令4条の3第2項1号の被合併法人と合併法人との間の関係と同項2号の「一の者」によって被合併法人と合併法人の全株式が保有される関係のそれぞれの規定の中でその2つの枠組みで捉えられた「完全支配関係」という用語を用いる、ということになっているため、同項1号及び2号の規定が、「完全支配関係」という用語を正しい内容に置き換えた場合に、文章として適切なものとならない、という問題が生じている(同前Q14・15参照)。
この法人税法施行令4条の3第2項2号の「同一の者」には個人の場合の特別な定めは設けられていないが、これには上記の法人税法施行令4条の2第2項前段の「一の者」の括弧書きと同様の括弧書きが設けられているものとして解釈をする必要があると考える(同前Q16参照)。以下、そのような前提に立って説明を行うこととする。
平成22年度改正後においては、立法担当者は、上記の法人税法2条12号の7の6の「一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」に関し、同改正前とは異なり、法人が100%グループの中に存在している法人であるのか否かという観点からではなく、その文言そのままに、相互に100%の資本関係にあるのか否かという観点から同号に該当するのか否かを判定すると説明している。平成22年度改正前は、グループ内の組織再編成であれば適格となるという考え方に基づいて制度と法令の規定が作られているという前提に立って組織再編成税制の各規定を解釈することとされていたため、そのように判定するとは解されていなかったわけであるが、解釈変更の理由は明らかではないものの、同改正後は、そのように判定すると説明されている。
上記の法人税法2条12号の7の6の「一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係」に関してこのような平成22年度改正後の解釈を採るということになると、同号と同じような規定となっている上記の法人税法施行令4条の3第2項2号に関しても、同様の解釈を採ることとせざるを得ない。前者の解釈は変更し、後者の解釈は変更しない、ということでは、説明不能となってしまう。
このように、法人税法施行令4条の3第2項2号に関して、被合併法人と合併法人が100%グループの中に存在しているのか否かという観点をなくして、被合併法人と合併法人に100%の資本関係があるのか否かという判定をするということになれば、必然的に、同号の「同一の者」に関しては、被合併法人又は合併法人の株主のみが該当すると解さざるを得ない。
このような解釈は、株主が兄弟の関係にある会社の株式を同時に他の株主に譲渡した場合に支配関係や完全支配関係が継続するという解釈(同前Q11参照)と整合するものである。
(2)平成22年度改正後の規定による完全支配関係の判定
法人税法施行令4条の3第2項2号の「同一の者」が上記(1)で述べたように解釈することとなるということを踏まえて、各ケースについて、平成22年度改正後の規定によって完全支配関係の判定を行うとすればどのようになるのか、ということを考えてみよう。
① ケース1
このケース1(図表4参照)においては、各法人の株主はそれぞれ1人しかおらず、甲と丁は親族関係にないため、甲と丁がそれぞれ株式のすべてを保有するA社とD社に関しては、完全支配関係がない、ということになる。
このように、ケース1に関しては、平成22年度改正の前後で結論が異なることとなる。
【図表4】ケース1
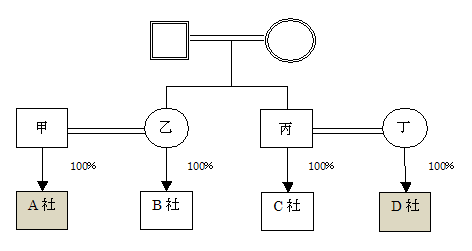
② ケース2
このケース2(図表5参照)においても、上記のケース1の場合と同様に、甲と丁は親族関係にないため、甲と丁が株式のすべてを保有するA社とD社に関しては、完全支配関係がない、ということになる。
このように、ケース2に関しても、平成22年度改正の前後で結論が異なることとなる。
【図表5】ケース2
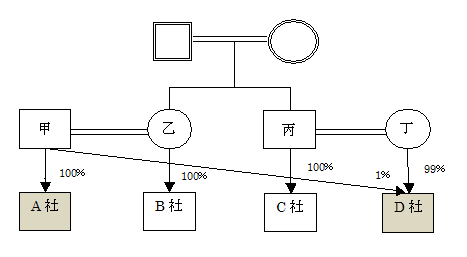
③ ケース3
このケース3(図表6参照)においては、A社とD社の株主は甲、乙、丁であり、乙から見ると甲も丁も親族となるため、A社とD社に関しては、乙とその親族がすべての株式を保有していることとなって、完全支配関係がある、ということになる。
このように、ケース3に関しては、平成22年度改正の前後で結論は同じとなる。
【図表6】ケース3