
日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


※T&Amaster(ロータス21)2011.9.19 No.419に掲載
当社(P社)は、3年前にA社の発行済株式の100%を購入し、当社グループの事業を多角化することを企図しましたが、計画通りに行かず、昨年、A社を解散させ、本年には、残余財産の確定を経て清算することとしています。
このA社には、株式の購入時に、資産に含み損はありませんでしたが、過去の欠損金があったため、法人税法57条の2(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の適用を受けることとならないのかという検討を行いました。
その結果、当社(P社)はA社の株式の100%を買い取る前にA社の債務の総額の80%に相当する債務に係る債権をその金額の40%相当額で買い取っていますので、法人税法57条の2第1項3号に該当する可能性がありますが、A社は資金借入れ等を行っていないため、同号の適用事由にも該当しないこととなっており、A社において、過去の欠損金の繰越控除を行ってまいりました。
しかし、平成22年度改正において、残余財産の確定が同制度の適用事由(法法57の2①四)に追加された中で、本年、A社の残余財産の確定と清算を行うこととなりましたので、改めて、A社の残余財産の確定の日の属する事業年度における過去の欠損金の繰越控除の可否とA社の欠損金の当社(P社)への引継ぎの可否についてご教授をお願いしたいと存じます。
なお、A社における各事業年度の欠損金等の発生状況、A社の発行済株式の100%を購入した日(特定支配日)、解散の日、残余財産の確定の日(予定)等は、次の図のとおりです。
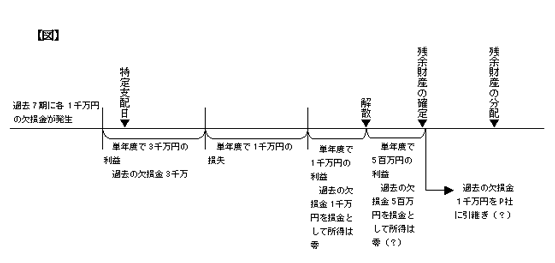
要 旨
【マエストロの解説】
特定支配日前に欠損等法人の解散が行われている場合には、残余財産の確定により、欠損等法人においては過去の欠損金の繰越控除ができなくなり、その株主においてはその欠損等法人の過去の欠損金の引継ぎを受けることができなくなる。
しかし、ご質問のケースにおいては、特定支配日以後に欠損等法人であるA社の解散が行われているため、残余財産が確定した場合であっても、A社においては過去の欠損金の繰越控除が可能であり、完全支配関係にある株主であるP社においてはA社の過去の欠損金の引継ぎを受けることができることとなると解される。
1 本制度の趣旨
平成18年度改正において、「特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」の制度が創設された。
本制度は、他の者によって支配されることとなった「欠損等法人」について、青色欠損金の繰越控除を認めない措置(法法57の2)と資産の含み損の利用を制限する措置(法法60の3(旧法法60))から成っている(注)。
(注)連結納税制度においても同様の観点から措置が講じられているが、以下の解説は、単体納税制度を前提として行っている。
本制度の趣旨に関しては、次のように説明されている。
「 最近、このような欠損金の繰越控除の仕組みを利用し、欠損金を有する法人を買収した上で利益の見込まれる事業をその法人に移転することによって課税所得を圧縮するといった租税回避行為が多く見受けられるようになってきたところです。
そこで、今回の税制改正において、このような租税回避行為を防止するため、欠損金を利用するための買収と認められる場合に、その買収された法人の欠損金の繰越控除を認めない措置が講じられたものです。また、このような租税回避行為は、欠損金に限らず資産の含み損を利用しても可能となることから、欠損金を有する法人のみならず、資産の含み損を有する法人も本措置の対象とするとともに、その含み損を実現した場合についてもこれを制限する措置も講じられています。」(『平成18年度 税制改正の解説』(財務省)352頁)
2 本制度の概要
本制度の概要に関しては、次のように説明されている。
「 法人で他の者との間に他の者による特定支配関係を有することとなったもののうち、その特定支配関係を有することとなった日(以下「支配日」あるいは「特定支配日」といいます。)の属する事業年度(以下「特定支配事業年度」といいます。)において特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額又は評価損資産を有するもの(以下「欠損等法人」といいます。)が、その支配日以後5年を経過した日の前日までに適用事由に該当する場合には、その該当することとなった日(以下「該当日」といいます。)の属する事業年度(以下「適用事業年度」といいます。)以後の各事業年度においては、その適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、法人税法第57条第1項の規定は適用しないこととされました(法法57の2)。」(同前353頁)
この「特定支配関係」とは、「他の者(省略)と法人との間の当該他の者による支配関係(省略)とする」(法令113の2①)とされている。
(注)この「支配関係」とは、法人税法2条12号の7の5(支配関係の定義)に定義されており、発行済株式等の50%超の株式等を直接又は間接に保有する関係又は一の者によって双方の法人が発行済株式等の50%超の株式等を直接又は間接に保有される関係である。
本制度は、支配日以後5年を経過した日の前日までに「適用事由」のいずれかに該当することとなった場合に適用されることとなるわけであるが、この「適用事由」とは、次の事由とされている(法法57の2①一~五)。
イ 欠損等法人が特定支配日の直前に事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、その特定支配日以後に事業を開始すること(清算中のその欠損等法人が継続することを含む。)(法法57の2①一)
(注)この「特定支配日」とは、特定支配関係を有することとなった日とされている(法法57の2①)。
ロ 欠損等法人が特定支配日の直前に営む事業(以下「旧事業」という。)のすべてを特定支配日以後に廃止し又は廃止することが見込まれている場合に、その旧事業のその特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れを行うこと(法法57の2①二)
ハ 他の者又は当該他の者の関連者が当該他の者又は関連者以外の者から欠損等法人に対する特定債権を取得している場合(その特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、その特定債権につきその特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合等を除く。)に、その欠損等法人が旧事業のその特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと(法法57の2①三)
(注)この「特定債権」とは、欠損等法人に対する債権で、その取得の対価の額がその債権の額の50%未満であり、かつ、その債権の額の取得の時におけるその欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が50%超である場合のその債権とされている(法令113の2⑲)。
二 上記イ若しくはロの説明文中にある「場合」又はハの特定債権の取得が行われている「場合」において、欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又はその欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること(法法57の2①四)
<参考>実務においては、発行済株式のすべてを取得して100%子会社とした法人について、吸収合併を行うのか、あるいは、清算を行うのかということが検討課題となることがあるため、この100%子会社が欠損等法人に該当し、かつ、その欠損等法人の吸収合併を行うという場合の取扱いについて、確認を行っておくこととする。
この100%子会社が、欠損等法人で、上記イ若しくはロの説明文中にある「場合」又はハの特定債権の取得が行われている「場合」に該当する場合において、その吸収合併が適格合併であるときは、その欠損等法人の最後事業年度(合併の日の前日の属する事業年度)が法人税法57条の2第1項の「適用事業年度」となり、その最後事業年度に利益が生じたとしても、同項の規定により、過去の欠損金を損金とすることはできず、同条5項の規定により、その欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度の欠損金を合併法人に引き継ぐこともできない。
また、その吸収合併が適格合併である場合において、最後事業年度に利益が生じないときは、法人税法57条の2第1項の規定の適用はなく、同条5項の規定によって合併法人への引継ぎが制限されるのも最後事業年度前の各事業年度の欠損金であるため、その最後事業年度の欠損金についは、57条2項の引継ぎの規定に該当し同条3項の引継ぎ制限の規定に該当しなければ、合併法人に引き継ぐことができることとなる。
なお、その吸収合併が非適格合併である場合には、その欠損等法人の最後事業年度において、過去の欠損金を損金とすることができるが、合併法人への欠損金の引継ぎはできないこととなる。
ホ 欠損等法人が特定支配関係を有することとなったことに基因して、その欠損等法人のその特定支配日の直前の社長等の役員のすべてが退任等を行い、かつ、その特定支配日の直前にその欠損等法人の業務に従事する使用人(旧使用人)の総数のおおむね20%以上に相当する者がその欠損等法人の使用人でなくなった場合において、その欠損等法人の非従事事業(旧使用人がその特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業)の事業規模が旧事業のその特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(法法57の2①五)
また、本制度は、上記の適用事由の発生期間である「支配日以後5年を経過した日の前日まで」という期間について、次の事実が生じた場合には、その事実が生じた日までに短縮することとされている(法令113の2⑧・⑨・⑩)。
ⅰ 他の者が有する欠損等法人の株式等が譲渡されたことその他の事由により、その欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなったこと(法令113の2⑧)
ⅱ 欠損等法人が債務者から受ける債務の免除又は欠損等法人が債務者から受ける自己債権の現物出資により、その欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額がその欠損等法人のその免除又は現物出資の日の属する事業年度開始の時の欠損金額のおおむね90%を超える場合におけるその免除又は現物出資(法令113の2⑨)
ⅲ 更生手続開始の決定等(法令113の2⑩一)
ⅳ 解散(解散後の継続又は一定の資金借入れ等の見込みがないものに限り、欠損等法人の特定支配日前の解散及び合併による解散を除く。)(法令113の2⑩二)
3 ご質問のケースの検討
A社の欠損金の取扱いにつき、P社による株式の買取り日の属する事業年度、その翌事業年度、解散の日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度に分けて、解説することとする。
(1)P社による株式の買取り日の属する事業年度における取扱い
P社は、A社の株式の100%を買い取る前に、A社の債務の総額の80%に相当する債務に係る債権をその金額の40%相当額で買い取っているため、上記2ハの説明文中にある「場合」に該当することとなる。
ただし、A社は、旧事業の同日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行っていないことから、ご指摘のとおり、上記2ハの事由には該当しないこととなる。
このため、A社は、過去7期の欠損金7千万円のうち、当該事業年度の所得の金額3千万円に達するまでの金額について、当該事業年度の損金に算入することができることとなる。
この結果、当該事業年度においては、所得は発生しないこととなる。
(2)P社による株式の買取り日の属する事業年度の翌事業年度における取扱い
A社においては、P社による株式の買取り日の属する事業年度の翌事業年度は、1千万円の損失が生じているため、過去の累積の欠損金額は、5千万円(7千万円 - 3千万円 + 1千万円)となり、これを翌事業年度以後に繰り越すこととなる。
(3)A社の解散の日の属する事業年度における取扱い
A社は、P社がA社の株式の買取りを行った日の属する事業年度の翌々事業年度の中途において解散しているため、ご質問文にあるとおり、翌々事業年度開始の日から解散の日までの期間がみなし事業年度となる(法法14①一)。
A社は、このみなし事業年度において、1千万円の利益が生じている。
このため、このみなし事業年度における1千万円の利益から過去の欠損金を控除してこのみなし事業年度に所得が発生しないようにすることができるのか否かということが問題となる。
この点に関しては、上記①で述べたとおり、本件は、上記2ハの説明文中にある「場合」に該当することとはなるが、上記2イからホまでに掲げた事由のいずれにも該当しないため、過去の欠損金1千万円を損金に算入し、このみなし事業年度においては、所得を発生させないこととなる。
(4)A社の残余財産の確定の日の属する事業年度における取扱い
A社が解散した後、事業年度終了の日の前に残余財産が確定するということになると、その解散の日の翌日からその残余財産が確定する日までの期間がみなし事業年度となり(法法14①二十一)、このみなし事業年度がA社の税制上の最後の事業年度となる。
A社は、この最後の事業年度において、5百万円の利益が生じているため、この最後の事業年度においても、過去の欠損金を損金とすることができるのか否かということが問題となる。
この最後の事業年度においては、P社がA社の発行済株式の100%を保有しているため、本制度の適用事由である上記2ニに掲げた「欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること」(法法57の2①四)に該当することとなり、本制度が適用される可能性がある。
しかし、本件に関しては、本制度の適用事由の発生期間を短縮する事実として上記2ⅳにおいて述べた「解散」に該当するものでないかという点の検討も必要となる。
この上記2ⅳは、法人税法施行令113条の2第10項2号に掲げられている「解散」を指しているが、同号括弧書きにおいては、この「解散」から「特定支配日前の解散」が除かれている。
換言すれば、本制度の適用事由の発生期間を短縮することとなる「解散」から、特定支配日以後の解散は除かれておらず、欠損等法人が特定支配日以後に解散をした場合には、本制度の適用事由の発生期間を短縮する「解散」が行われていることとなり、上記2ニに掲げた本制度の適用事由に該当したとしても、その適用事由の発生する時期が「解散」によって短縮された発生期間の後となるため、本制度の適用はない、ということになる。
<備考>法人税法施行令113条の2第10項2号に掲げられている「解散」の括弧書きにおいては、「特定支配日(省略)前の解散及び合併による解散を除く」とされており、特定支配日前の解散と特定支配日以後の解散とを区別して取り扱うという考え方に立たなければそのような定め方はしない規定となっている。
平成22年度改正において、清算所得課税を廃止し、自己の過去の欠損金を繰り越して使用することができる事業年度が増えることとなっているが、それは、上記の特定支配日前の解散と特定支配日以後の解散とを区別して取り扱うという考え方を変更しなければならない理由となるものではなく、現に、法人税法施行令113条の2第10項2号の規定の改正は行われていない。
このため、このみなし事業年度における5百万円の利益から過去の欠損金を控除し、このみなし事業年度においては、所得を発生させないこととなる。
また、平成22年度改正において、完全支配関係のある内国法人の残余財産が確定した場合には、その内国法人の欠損金をその完全支配関係がある株主である内国法人に引き継ぐことができることとされているため(法法57②・③)、本件においては、A社の欠損金をP社に引き継ぐことができるのか否かということも、問題となることとなる。
本件に関しては、A社の欠損金をP社に引き継ぐことができるのか否かは、適格合併と残余財産の確定の場合における欠損金の引継ぎの制限について定めた法人税法57条の2第5項の規定に該当するのか否かによって判定することとなるが、残余財産が確定したケースに同項の規定を当てはめるという前提に立って、同項の規定を要約すると、次のとおりとなる。
「 内国法人との間に前条第二項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人の残余財産が確定する場合には、その欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。」
この「適用事業年度」とは、支配日以後5年を経過した日の前日までに本制度の適用事由に該当することとなった日の属する事業年度(法法57の2①各号列記以外の部分)とされており、法人税法57条の2第5項においては、同条1項の規定の適用がある場合に上記の欠損金の引継ぎを制限することとされているわけである。
すなわち、法人税法57条の2の規定においては、1項によって欠損等法人が過去の欠損金の繰越控除が認められない場合には残余財産の確定による株主への欠損金の引継ぎも認められず、反対に、欠損等法人が過去の欠損金の繰越控除が認められる場合には残余財産の確定による株主への欠損金の引継ぎも認められる、ということになる。
ただし、残余財産の確定の場合に株主の欠損金とみなす金額を制限する規定である法人税法57条3項においては、支配関係事業年度前の各事業年度の欠損金について、株主の欠損金とみなす金額に含めないこととしている。
<参考>適格合併の場合にみなし共同事業要件を設けて支配関係事業年度前の各事業年度の欠損金の引継ぎを認めているにもかかわらず、残余財産の確定の場合に一律に支配関係事業年度前の各事業年度の欠損金の引継ぎを認めないこととしている理由については、「清算の場面の実態に合わないことから、みなし共同事業要件に該当する場合の制限の除外措置は設けられていません」(『平成22年度 税制改正の解説』(財務省)286頁)と説明されている。
このため、本件においては、A社において繰越控除を行うことができずに残った欠損金3千5百万円(7千万円 - 3千万円 + 1千万円 - 1千万円 - 5百万円)のうち、特定支配日の属する事業年度前の事業年度に生じた金額2千5百万円(7千万円 - 3千万円 - 1千万円 - 5百万円)はP社に引き継ぐことができず、上記(2)のP社による株式の買取り日の属する事業年度の翌事業年度における欠損金の1千万円のみをP社に引き継ぐこととなる。
<備考>法人税法57条の2第1項4号においては、本制度の適用事由として、「欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること」という文言が平成22年度改正で追加されている。
また、上記のとおり、平成22年度改正においては、法人税法57条の2第5項の規定により、欠損等法人の適用事業年度前の各事年度欠損金について、残余財産が確定した場合であっても、株主に引き継がせないこととされた。
これらの措置に関して、『平成22年度 税制改正の解説』(財務省)においては、次のように説明されている。
「 これにより、上記イ(法人税法57条の2第1項4号の残余財産の確定に関する部分の定め:著者注)により繰越控除の不適用となるだけでなく、残余財産の確定によって他の法人への引継ぎもできないこととされます。」(286頁)
この説明は、法律の規定の説明として述べられているものであるが、政令によって適用事由の発生期間の短縮まで加味して読んだ場合にも、欠損等法人における過去の欠損金の繰越控除の不適用と残余財産の確定による他の法人へのその引継ぎに不整合があるわけではなく、説明内容に疑義はない。
仮に、欠損等法人の解散が特定支配日前であるのか特定支配日以後であるのかにかかわらず、残余財産の確定を以って、欠損等法人における過去の欠損金の繰越控除を行わせないこととするとともに、他の法人にその引継ぎを行わせないこととするということであれば、平成18年度改正における考え方を変更する理由を明らかにするとともに、法人税法施行令113条の2第10項2号の規定の改正を行うことが必要となる。
なお、法人税法施行令113条の2第10項2号の規定は、「解散」が合併による解散を含むにもかかわらず重複排除が行われていなかったり、「合併による解散」の時期が明確でないなどの課題も見受けられる状態となっているため、同号の改正を行う場合には、平成18年度改正における取扱いの適否等から改めて検討を行った上で、改正を行う方がよいと考えられる。
ただし、上記(1)から(4)までの解説は、法人税法132条(同族会社等の行為又は計算の否認)の規定の適用がないという前提に立って行ったものであり、欠損等法人の株式等の買取りを行う場合には、57条の2の規定によって欠損金の繰越控除の制限等を受けないこととなるときであっても、132条の規定の適用を受けることとならないのかという検討が不可欠である点に十分に留意する必要がある。