
日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


※T&Amaster(ロータス21)2012.01.23 No.435に掲載
法人が「資本の払戻し」を行った場合には、法人税法施行令8条1項16号(資本の払戻し等の場合の資本金等の額の減少額)において、「減資資本金額」を資本金等の額の減少額とすることとされており、この「減資資本金額」は、「資本の払戻し等の直前の資本金等の額」に、次のイに掲げる金額のうちのロに掲げる金額の割合を乗じて計算した金額とされています。
イ 当該資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(省略)終了の時の資産の帳簿価額から負債(省略)の帳簿価額を減算した金額(省略)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(省略)
この法人税法施行令8条1項16号の定めによると、上記ロの「(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)」という括弧書きは、「当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額」の読替えとなっており、「当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」の読替えとはなっていないため、法人が「適格現物分配」に該当する「資本の払戻し」を行った場合であっても、「当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」を用いて計算した割合に基づき、減少させる資本金等の額を計算することとなるはずです。
ところが、『平成22年度 税制改正の解説』(財務省)には、次に掲げたとおり、「適格現物分配」に該当する「資本の払戻し」の場合には「交付資産の簿価」を用いて計算した割合に基づき、減少させる資本金等の額を計算している処理例(214頁)が示されています。法人の行った「資本の払戻し」が「適格現物分配」に該当する場合、その法人が減少させる資本金等の額はどのように計算するべきなのでしょうか。
▼クリックすると拡大します。
要 旨
【マエストロの解説】
本件質問は、「適格現物分配」に該当する「資本の払戻し」を行った法人において減少させることとなる資本金等の額の計算に関する質問であると同時に、「適格現物分配」に該当する「資本の払戻し」を受けた株主においてみなし配当とする金額の計算に関する質問ともなるわけであるが、結論を先に述べれば、基本的には、『平成22年度 税制改正の解説』の処理例から推測される立法者の意図を根拠とし、法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きの定めをこの処理例のとおりに解釈するのが適当であると考えられる。
法人税法施行令8条1項16号に関しては、平成22年度改正において「現物分配」と「適格現物分配」の仕組みを創設したことから(注1)、同号ロに「(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)」という括弧書きを付する等の改正が行われているが、この改正の前提となっている「資本の払戻し等」に関する取扱いは、平成18年度改正によって大きく改正されて現在に至ったものである。
(注1)「現物分配」とは、法人がその株主等に対して剰余金の配当等により金銭以外の資産の交付をすることとされており(法法2十二の六)、「適格現物分配」とは、内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前においてその内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る)のみであるものとされている(法法2十二の十五)。
平成22年度改正以後も、「資本の払戻し等」を事由とする「現物分配」は、この平成18年度改正によって改正された「資本の払戻し等」に関する取扱いに拠ることとなっており、それを前提として、「資本の払戻し等」を事由とする「適格現物分配」の取扱いが設けられているため、まず、この平成18年度改正について、その内容をよく確認しておくことが必要となる。
なお、本件質問は、「資本の払戻し」が「適格現物分配」に該当する場合の取扱いに関するものであるため、本稿では、「資本の払戻し」の取扱いを中心として解説を行っている。
1.平成22年度改正前の「資本の払戻し」の取扱い
(1)平成18年度改正前の「減資等」の取扱い
平成18年度改正前においては、「資本の減少」を含む「減資等」に際しては、「減資資本等金額」(旧法法2十七ツ、旧法令8の2⑨)を減少させることとされており、その金額は、次のとおりとされていた(注2)。
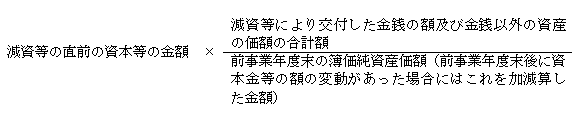
(注2)以下、説明を簡素化するために、「資本の払戻し」を行う法人の株式については、その全てを親会社が保有しているものとし、商法又は会社法上の制約は考慮しないものとする。
この取扱いは、平成13年度改正において定められたものであり、同改正においては、法人の商法上の処理や企業会計上の処理の如何にかかわらず、法人税法においては現に行われた取引をみてその実態に即した取扱いとする、という考え方が採られていたために、「減資等」に関しても、そのような観点に立って取扱いが定められていた。
この平成13年度改正の考え方と取扱いに関しては、現実にどのような取引が行われているのかということが問題であり、基本的には、どのような会計処理が行われているのかということは問題とならないため、仮に、法人が会社法によって新たに設けられた「剰余金の配当」によって「減資等」を行うとしても、その「剰余金の配当」のうち法人税法上の「減資等」に該当する部分を画定すれば、そのままその部分に適用することが可能であったものである。
この平成13年度改正における取扱いに関して、法人が資本剰余金と利益剰余金の双方を減少させて剰余金の配当として含み益のある資産を株主に交付したと仮定して処理例を示すと、図1のとおりとなる。
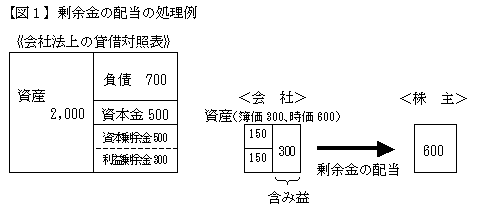
図1の場合、会社は「剰余金の配当」として剰余金300(資本剰余金150、利益剰余金150)を減少させて資産300(時価600)を株主に交付しているが(注3)、法人税法上の処理を行うに当たっては、この会社と株主との間の「剰余金の配当」の取引に関して、資本剰余金の減少額に対応する部分の金額(簿価150+含み益150=300)が「減資等」の対価として交付され、利益剰余金の減少額に対応する部分の金額(簿価150+含み益150=300)が配当等として交付されたという事実認定を行い得るものとする。
(注3)本稿における以下の法人税法上の処理例においては、いずれも、会社と株主との間に図1の状態の取引があるものとする。
この場合、法人税法上の処理は、図2のとおりとなる。
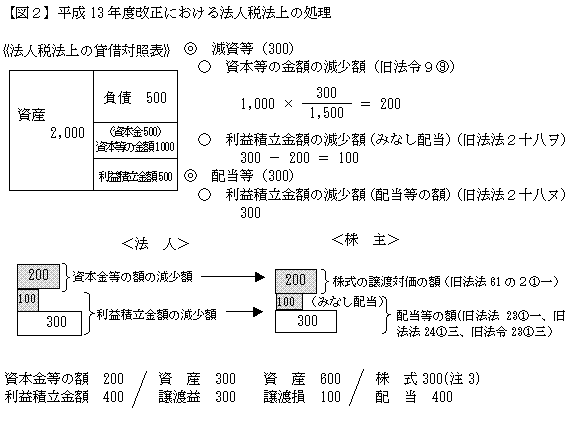
(注)株主における株式の譲渡原価は、『平成22年度 税制改正の解説』の処理例と同様に、300であるものとする。
図2の処理例の網掛けの部分は、法人と株主との間の「減資等」の取引を示しており、「利益積立金額(みなし配当)」100は、法人が資本部分のみを減少させて金銭等を交付する処理を行ったとしても、法人税においては、その取引の経済実態に着目し、その金銭等の額の一部に配当等の額とみなすべき部分がある、という認識の下に、配当等の額とみなして取り扱うこととしているものである。
(2)平成18年度改正以後の「資本の払戻し」の取扱い
①「資本の払戻し」に関する平成18年度改正の概要
平成18年度の「資本の払戻し」に係る改正は、「会社法の制定により、株式会社の株主に対する会社財産の払戻しについては、従前の利益の配当及び中間配当は利益剰余金を原資とする剰余金の配当と、株式の消却を伴わない資本の減少は資本金の資本剰余金への振替え及び資本剰余金を原資とする剰余金の配当と整理されたこと」(『平成18年度 税制改正の解説』262頁)を理由として行うものとされている。
この平成18年度改正の際においては、同改正前の取扱いを次のように捉えていた。
「 法人税法では従来、払戻しの手続きの違い(資本の減少による会社財産の流出か、配当による会社財産の流出か)に応じて、株主等の持株関係に変動がない場合における株主に対する会社財産の払戻しについて、利益のみの払戻しかそれ以外の払戻し(資本部分と利益部分とが比例的に払い戻される払戻し)かを規律していました。」(同前261・262頁)
平成18年度改正においては、これを次のように改めることとしたと説明している。
「 今後は、手続きではなく払戻し原資に着目することとし、払戻し原資が利益剰余金のみである場合には利益部分の払戻し(法法23①の配当等)と、払戻し原資に資本剰余金が含まれている場合にはそれ以外の払戻し(資本部分と利益部分の払戻し(法法24①三のみなし配当))と規律することとしたものです。」(同前262頁)
この平成18年度改正により、利益剰余金を原資とする剰余金の配当の額は、その全額が株主に対する法人税法23条1項(受取配当等の益金不算入)の配当等の額とされ、また、資本剰余金を原資とする剰余金の配当の額は、株主に対する資本金等の額の払戻しと配当等の額とされることとなった。
この資本剰余金を原資とする剰余金の配当において株主に対する資本金等の額の払戻しとして資本金等の額を減少させることとなる金額は、次の計算式によって計算した金額とされている。
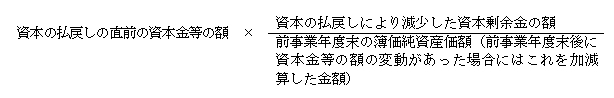
このような改正により、どのような結果となるのかということに関しては、次のように説明されている。
「 資本剰余金と利益剰余金の双方を同時に減少して剰余金の配当を行った場合には、全体が資本の払戻しとなるものの、上記算式の分数の分子が「交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額」ではなく「減少した資本剰余金の額」とされているため、資本剰余金の減少額の範囲内でまず資本金等の額が減少し、交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちその減少資本金等の額を超える部分の金額が利益積立金額の減少額(株主にとってはみなし配当の額)となります。つまり、資本剰余金原資部分は、資本金等の額と利益積立金額との比例的減少と、利益剰余金部分は利益積立金額の減少となるということです。」(同前256・257頁)
そして、含み益のある資産を交付した場合に関しては、次のように説明されている。
「 子会社から親会社への配当など、会計上含み益を計上しない現物配当を資本剰余金を原資として行った場合には、資本剰余金の減少部分は資本金等の額と利益積立金額の比例的減少となり、含み益部分は利益積立金額の減少となります。」(同前257頁)
②「資本の払戻し」に関する平成18年度改正の検討
上記①の平成18年度改正に関しては、払戻しの「手続き」の違いではなく払戻しの「原資」の違いに着目して払戻しの内容を規律することとしたとされているが、この点に関しては、もう少し、その詳細を確認しておく必要がある。
平成18年度改正は、上記①において確認したとおり、利益剰余金を原資とした剰余金の配当に関してはその全てを配当等の額とし、資本剰余金を原資とした剰余金の配当に関しては資本部分と利益部分の双方の交付としたという点では、確かに、払戻しの「原資」の違いに着目して払戻しの内容を規律することとした、ということとなっている。
しかし、原資の違いにより、その全額を利益部分の交付とするものと、資本部分と利益部分の双方の交付とするものとを分けるということだけであれば、平成18年度改正前に、その全額を利益部分の交付とするものとされていた「利益の配当」と、資本部分と利益部分の双方の交付とするものとされていた「減資等」から成る構造を変更する必要はなく、「利益の配当」とする部分と「減資等」とする部分とをどのように分けるのかということを示せばよいだけ、ということになる。平成18年度改正前の上記(1)の冒頭に掲げた計算式における分数の分子は「減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額」となっているが、同改正後の上記①の計算式における分数の分子は「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」となっており、この相違は、払戻しの「原資」の違いに着目して取扱いを変更したということでは説明できないものである。
ところで、上記(1)の計算式と①の計算式に眼を向けてみると、これらの計算式の金額は、株主に金銭のみが交付される場合には、分数の分子の金額に相違が生じないため、同額となるが、株主に含み損益のある資産が交付される場合には、分数の分子の金額が異なることとなるため、同額とはならない。
平成18年度改正以後の上記①の計算式においては、分数の分子の金額が「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」となっているため、株主に交付される資産の含み損益の如何によって金額が異なることはない。
これに対して、平成18年度改正前の上記(1)の計算式においては、分数の分子の金額が「減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額」となっているため、株主に交付される資産に含み益がある場合には大きな金額が算出され、含み損がある場合には小さな金額が算出されることとなる(注4)。
(注4)このように、平成18年度改正前において、株主に交付される金銭の額及び金銭以外の資産の価額に基づき、減少させる資本金等の額(同改正前は、資本の金額と資本積立金額)を計算することとされていたのは、「減資等」の取扱いも、商法や企業会計の処理に拠るのではなく法人税法の独自の観点に立って行うという考え方を基本として行われた平成13年度改正の一環として整理されていたためである。
このような点からすると、平成18年度改正において、上記(1)の計算式における分数の分子の金額の改正を行った理由は、上記①の末尾の引用文に示されているとおり、「会計上含み益を計上しない現物配当を資本剰余金を原資として行った場合」に、「資本剰余金の減少部分は資本金等の額と利益積立金額の比例的減少」とし、「含み益部分は利益積立金額の減少」とするために、上記(1)の計算式における分数の分子の金額を「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」としたものと考えられる(注5)。
(注5)剰余金の配当として金銭又は含み損益のない資産を交付した場合には、上記①の計算式における分数の分子の「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」は「減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額」と同額となるため、この後者を前者に変更する必要はないこととなる。
これを処理例で確認すると、図3のとおりである。
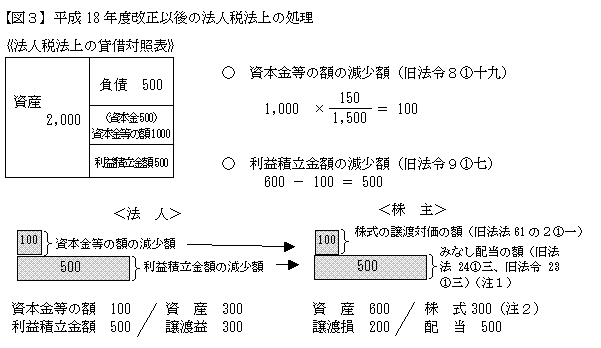
(注1)法人税法23条1項1号においては、剰余金の配当に関して、「資本剰余金の額の減少に伴うもの・・・を除く」とされており、24条1項3号においては、資本の払戻しに該当する剰余金の配当に関して、「資本剰余金の額の減少に伴うものに限る」とされているため、剰余金の配当の原資に一部でも資本剰余金がある場合には、その剰余金の配当の全てが24条1項3号の適用対象となり、利益積立金額の減少に対応する部分の金額は、全てみなし配当の額とされることとなっている。
本来、みなし配当は、会社法等において法人税法23条1項の配当等の額とされないものについて、法人税法上、配当等の額とみなすこととするものであり、会社法上の処理において利益剰余金を原資とする部分に関しては、24条1項3号の規定を適用してみなし配当とした上で23条1項の配当等の額としなければならないものであるのか、また、資本剰余金を原資とする部分と利益剰余金を原資とする部分の区分は、本来は、事実認定の問題ではないのか、という疑問が残らざるを得ない。
(注2)株主における株式の譲渡原価は300であるものとする。
図3の処理例においては、法人の資本剰余金の減少額150を上記①の計算式における分数の分子として計算した100のみが法人税法上の資本金等の額の減少額とされているわけであるが、上記注4においても述べたとおり、事実認定により、剰余金の配当600(含み益300を含む)のうち、資本剰余金を原資とする部分を300(含み益150)とし、利益剰余金を原資とする部分を300(含み益150)とするという選択肢もあったものと考えられる。
しかし、現実には、このように、事実認定に基づき、税法上の観点から、配当等の額とする金額と、「資本の払戻し」とする金額及びみなし配当とする金額とを決めるという選択肢は、採用されず、会社法上の資本剰余金の減少額に基づいて「資本の払戻し」とする金額(資本金等の額の減少額)及びみなし配当とする金額(利益積立金額の減少額)を決めることとされているわけである。
その結果、図3の処理例のみなし配当の額は資産の含み益300の全額を含む500となり、上記①の末尾の引用にあるとおり、現物配当においては、法人税法上、資産の含み益部分の全額が利益積立金額の減少額となり、株主においてみなし配当の額とされることとなる。
ところで、このように「含み益部分は利益積立金額の減少とする」という判断は、確かに理に適ったもののようにも思われるが、理論と実態の双方の観点からよく考えてみると、疑問なしとしない。
図3の処理例の剰余金の配当が金銭で行われたとすると、法人税の処理においては、資本金等の額の減少額は200となり、みなし配当とされる金額は400となることになるが、この剰余金の配当について、金銭に代えて含み益のある資産を交付することとし、資本剰余金と利益剰余金を均等に150ずつ減少させたとすると、図3の処理例のとおり、資本金等の額の減少額が100、みなし配当とされる金額は500ということになる。
本来、みなし配当の規定は、法形式に拠るのではなく経済実態に即して取り扱うという趣旨で設けられているものであり、このように、経済実態が変わらないものについて、剰余金の配当が金銭で行われた場合と資産で行われた場合とでみなし配当とされる金額が異なることとなることを理論的に説明することは、容易ではない、と考えられる。
従来の「利益の配当」を「剰余金の配当」とした会社法における改正は、諸外国の会社法改正の動向を踏まえたものであると言われているが、このような流れにあっては、我が国の税法の採るべき道は、法形式に拠るのではなく、諸外国と同様に、税法の独自の観点から、資本取引と配当に関しても、取引の実態を見て認定を行う、ということではなかったかと考えられる。
平成18年度改正においては、会社法に依存した処理を行うことによって、法人税法における取扱いの理論的な説明が難しくなったり、実態に合わない取扱いとなってしまった部分がいくつか見受けられるわけであるが、この「資本の払戻し」の取扱いに関しても、もう少し検討の余地があったように思われる。
2.平成22年度改正以後の「資本の払戻し」における資本金等の額の減少額
平成22年度改正においては、既に述べたとおり、「適格現物分配の制度が創設されたが、内国法人が「適格現物分配」により被現物分配法人にその有する資産の移転をした場合には、その資産の「適格現物分配」の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとされている(法法62の5③)。
現物分配法人においては、「適格現物分配」の事由が「資本の払戻し」である場合には、法人税法施行令8条1項16号ロにより資本金等の額の一定額を減少させ、9条1項11号により利益積立金額の一定額を減少させることとされている。そして、この法人税法施行令8条1項16号ロに、「(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)」という括弧書きが追加されることとなっており、本件質問は、法人税法施行令8条1項16号ロの「当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」に関しても、この括弧書きの置換えの定めが働くのか否か、というものとなっているわけである。
この括弧書きの定めが「当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額」に対して働き、「資産」が「適格現物分配に係る資産」である場合には、「価額」が「その交付の直前の帳簿価額」に置き換わることになるということに関しては、疑問の余地はない。
しかし、質問文にもあるとおり、「資産」という用語が含まれない「当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」に対しては、上記の括弧書きの置換えの定めは、本来、働かないはずである。上記の括弧書きの置換えの定め方は、それを「当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額」に対してのみ働かせて「当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」に対しては働かせない仕組みとしようとする場合に採られる定め方と同様となっている。
それにもかかわらず、『平成22年度 税制改正の解説』においては、「資本の払戻し」が「適格現物分配」に該当する場合に、上記の括弧書きの置換えの定めが働くものとして処理例を示しているわけである。
以下、この二つの取扱いのいずれが適切なものであるのかということを考えるに当たり、まず、それぞれの取扱いがどのような内容となっているのかということを確認することとする。
法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きの置換えが働かないと解釈する場合の取扱い(以下「処理例1」という。)は、図4のとおりである。
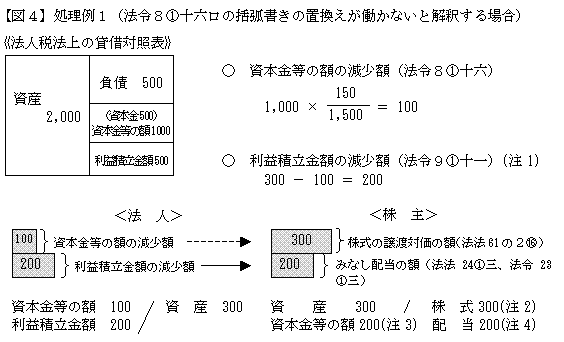
(注1)法人税法施行令9条1項11号においては、利益積立金の減少額を「第八条第一項第十六号に規定する合計額」に基づいて計算することとされており、この「合計額」は、「当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額」(法令8①十六)とされているが、この括弧書きの「(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)」は、資本の払戻し等が適格現物分配に該当する場合には、疑問の余地なく、働くこととなる。次の処理例においても、同様である。
(注2)株主における株式の譲渡原価は300であるものとする。
(注3)法人税法施行令8条1項17号により、譲渡損相当額は資本金等の額の減少額とすることとなる。
(注4)法人税法24条1項においては、「適格現物分配」の場合には、みなし配当とする金額の計算に用いる「金銭以外の資産の価額」について、「適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額」としている。そして、法人税法24条1項においては、みなし配当とする金額の計算に用いる「当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額」について政令に委任し、「資本の払戻し」に関しては、法人税法施行令23条1項3号において、「直前の資本金等の額・・・にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合・・・を乗じて計算した金額」を基にして計算するものと定め、同号イ及びロにおいて、質問文におけるイ及びロと殆ど同じ文言の定めを設けている。
すなわち、本件質問は、「適格現物分配」に該当する「資本の払戻し」を行った法人に
おいて減少させることとなる資本金等の額の計算に関する質問であると同時に、「適格現
物分配」に該当する「資本の払戻し」を受けた株主においてみなし配当とする金額の計算
に関する質問ともなっているわけである。
他方、法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きの置換えが働くと解釈する場合の取扱い(以下「処理例2」という。)は、図5のとおりである。
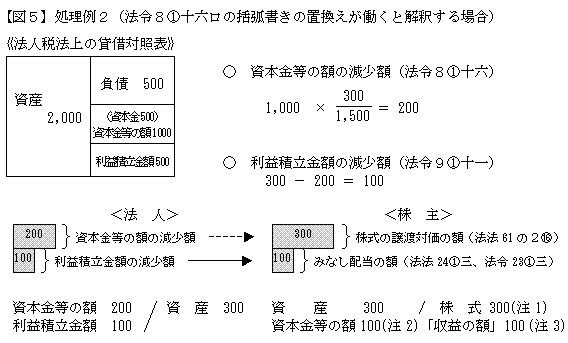
(注1)株主における株式の譲渡原価の額は、法人税法61条の2第17項及び法人税法施行令119条の9第1項において、所有株式の帳簿価額に「当該払戻し等に係る第二十三条第一項第三号(みなし配当金額の計算方法)に規定する割合」を乗じて計算した金額とされており、この割合は、法人税法施行令8条1項16号ロと同様に、「適格現物分配」の場合の取扱いに関する疑問が存在する状態となっているが、本例では、他の例との比較検討の都合上、300であるものとする。
(注2)処理例1と同様に、法人税法施行令8条1項17号により、譲渡損相当額は資本金等の額の減少額とすることとなる。
(注3)この法人税法62条の5第4項の「収益の額」は23条1項1号の「剰余金の配当等の額」ではないのか、なぜ「収益の額」としたのか、23条1項と同様の取扱いとしているにもかかわらず同項の適用対象から除いて62条の5第4項において取扱いを定めることとしたのはなぜか、といった疑問の声が聞かれる。
法人税法24条1項により、同項3号の金額を23条1項1号の金額とみなす取扱いは、23条1項の規定を適用する場合に止まらず、法人税法の全ての規定を適用する場合に適用されるため、62条の5第4項の規定を適用する場合にも、「資本の払戻し」によって生じた24条1項の「その超える部分の金額」は23条1項1号の「剰余金の配当等の額」とみなされることとなる。このため、法人税法62条の5第4項の「収益の額」は、23条1項1号の「剰余金の配当等の額」と同じものであると考えられる。
この金額を「剰余金の配当等の額」に含めずに「収益の額」とした理由や組織再編成に係る所得の金額の計算(第2編第1章第1節第6款)中の62条の5第4項において取扱いを定めることとしたことに関しては、その理由を明確に説明したものは見受けられないが、「適格現物分配」を資本等取引ではなく組織再編成と位置付けたことに因るものと推測される。
なお、「現物分配」や「適格現物分配」は、組織再編成ではなく、資本等取引であって、これらに関する税制は、本来、資本等取引税制として整備すべきことについては、拙著『詳解 グループ法人税制』(法令出版)の問103及び鼎談664頁を、また、法人が稼得した「所得」に対する課税を行わないまま「所得の分配」を行うことに関する疑問については、同じく問104を参照されたい。
本件のように法令の解釈に疑義がある場合には、それぞれの解釈に基づく取扱いを比較することによって、自ずといずれの解釈が妥当であるのかということが明らかになるというケースが多いわけであるが、本件に関しては、上記の二つの取扱いの内容を比較してみても、いずれが適切であるのかということを判断することは困難である。上記の二つの取扱いの中で、法人の資本金等の額の減少額がどのような金額となるのかということを問う本件の判断の手掛かりとなる可能性が最も高い部分は、株主における株式の譲渡対価の額であるが、これに関しては、処理例1においては、法人における資本金等の額の減少額100に対して300となっており、処理例2においては、同じく、200に対して300となっている。
法人が資本金等の額を減少させて交付した金額とそれを受けて株式の譲渡の処理を行う株主のその株式の譲渡対価の額とが異なるという現象は、平成22年度改正によって初めて生じたものであるが、これらの金額が異なるということは、法人が資本金等の額を減少させて金銭等を交付する行為とその金銭等の交付を受けて株主が株式を譲渡する行為とを「取引」として合理的に説明することができない、ということを意味している。
このような状態が生ずることとなったのは、平成22年度改正において、みなし配当が生ずる場合に株式の譲渡損益を計上させないようにするために株式の譲渡対価の額を譲渡原価の額に相当する金額としたためである。本来は、譲渡対価の額は、「取引」の相手方が交付した金銭等の額となるものであるが、みなし配当が生ずる場合の株式の譲渡に関しては、株式の譲渡損益を計上させないために、株式の譲渡対価の額を自己の譲渡原価の額としたことにより、この株式の譲渡が「取引」として合理的に説明することができないものとなっているわけである。平成22年度改正以後、このような状態は、みなし配当が生ずる場合の株式の譲渡の全ての場面で生ずることとなっている。
このような状況にあるため、本件に関して、適切な答を得ることは、容易ではない。
しかしながら、法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きの規定の仕方に立法技術上の難点があると考えると、事情は全く異なってくることとなる。
法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きの規定の仕方が正しいという前提に立つ限り、上記のように壁に突き当たらざるを得ないわけであるが、この括弧書きの規定の仕方に立法技術上の難点があり、立法者の意図が的確に条文に表現されていない、と解するとすれば、『平成22年度 税制改正の解説』の処理例と法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きの規定との不整合も説明が可能となる。
すなわち、立法者の意図は、「資本の払戻し」が「適格現物分配」に該当する場合にも、その「適格現物分配」によって交付される資産の帳簿価額が純資産の額に占める割合に基づいて資本金等の額を減少させようというものであり、そのような取扱いとしようということであれば、本来は、法人税法施行令8条1項16号ロに「(当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の一部の分配が適格現物分配に該当する場合には、当該適格現物分配により交付される資産のその交付の直前の帳簿価額)」というような文言の括弧書きを設けるべきであった、と解するとすれば、上記の不整合は容易に説明ができるわけである。
本件に関しては、このように解する他ない、と考えられる。
このように解するとすれば、法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きは、趣旨解釈により、「資本の払戻し」が「適格現物分配」に該当する場合には、その「資本の払戻し」に対しても働く、とするのが適切であるということになるものと考えられる。
ただし、法人税法施行令8条1項16号ロの括弧書きが「資本の払戻し」には働かない方が有利になるというケースにおいては、このように解することが適当であるのか否かという点に疑問が残ることは、否定できない。立法の難点は納税者の責に帰すべきものではなく、このようなケースにおいては、個別の実務対応も考慮されてよいものと考える。
なお、当然のことながら、制度の内容や法令の規定に疑義があるものに関しては早期に見直しを行って是正するべきである、ということを最後に付言しておきたい。